それでは、いよいよ本当の冒険の世界へあなたを誘おう。
…とかいって、トレランレースのレポートように、エイド間の詳細を綴ったところで、OMMは毎年開催場所が変わるので、まったくもって意味がない。
ていうか、エイドとかそもそもないし…
このエントリーを書き始めたいまこの現在進行形で、「このレースはどう振り返ったもんか」とうーむと唸っているのだが、一つ”いい切り口”を思い付いた。
あれだ。「事件ベース」で振り返ろう。
DAY1、DAY2という時系列に起きたことを並べるよりも、「事件ベース」で振り返っていったほうが、よりこのOMMというレースをわかってもらえる気がする。
なので、事件を思い付いた分だけ書いていくので、今回のレポートは何回に渡るのか不明だ(笑)まぁ「他人に降りかかっている事件や不幸の話はたいがい楽しいので(←性格悪いやつw)、気長にお付き合いいただければと思う。
なんにせよ、OMMという遊びは、極論、「次から次へと降りかかる『事件』に対してどう対処していくか」というゲームなので(という理解を僕はしている)、「事件」には事欠かない。
事実、前回の参戦レポート第1弾も、前日から始まった「事件」の話だ。
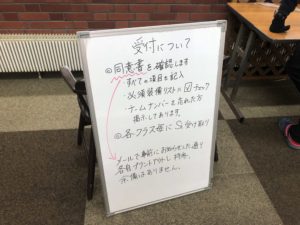
うん、これだ、しっくりきた。
「事件ベースでOMMを振り返る」。
これでいこう。
あ、でも「事件」がたくさん起こって、だからこそ「超楽しい」というお話が、OMMレポート全体を通して伝えたいことです。そんなことを書いてあるのが下記の記事。念の為。

事件その① スタート地点まで遠い
事件ベースで書くことを思い付いたはいいものの、そしたら一個目はこれになってしまった。まだレース始まらん(笑)
まぁこれは事件って程でもないのだけど。
結論から書くと、スタート地点は受付会場から徒歩40分程の場所にあった。しかも登った先。
正直別に大した距離ではないのだけど、遠い分、早く移動し始めなきゃならないので(当たり前か)、身を切るような寒さの中に早々に身を投じなければならないのだ。長野の朝は寒い。
今回は天気が良かったからよかったが、これが初っ端から雨だったらと思うと、、、萎える。


ちなみに事件①とは関係ないが、OMMのスタートについて少し。
下記がまさにOMMのスタート地点。ここからウェーブスタートで順々にスタートしていく。



事件その② 渡渉ポイントがやたら多い
渡渉とは「川を渡ること」をいうのだが、今回の地図はパッと見て「渡渉ポイント」が多いな、と感じた。
実際にはそこを渡るか渡らないかは自分次第なので、「渡渉ポイント」というよりは単純に「川がたくさんあった」というほうが、表現としては正しいかもしれない。
まだまだオリエンテーリング競技の経験の浅い僕らは、この「パッと見で川が多い」という地図の情報に危うく騙されるところだった。
川には当然「幅」がある。つまりは「川幅」のことなのだが、地図ではこの川幅に応じて、「川」と「小川」が太さで区別されていた。はじめこれを見落としていた。
そのため、川という川はすべて「渡れないもの」として認識してしまっており、それを前提としたルートファインディングをしていたのだ(つまりは遠回り)。
これは確か、1つ目のコントロールを発見し、「さぁ次のコントロールへはどう行こうか」と作戦を練っていたときのタイミングのこと。
1つ目のコントロールは川が周囲三方をU字に囲んでいる場所で、渡渉を避けるルートを選ぶと、今きた道を引き返してぐるっと回らなければいけなかった。
でもこれはさすがに非効率な気がしたので、
「いや、渡渉ダメとはいってるけど(←単なる勘違い)、ぶっちゃけどこかからは渡れんじゃね?」
という曖昧な認識のまま、とりあえず渡渉をするルートに進んだ(引き返さずに前に進んだ)。
とはいっても、やはり「もしほんとに渡れなかったら…」という不安もあったので、そこに向かっている途中に、マップの隅に小さく記載されている「地図記号とその説明文」を食い入るようにみた。この行動が正解だった。
先述したが、地図に示されている川は、「川」と「小川」で区別されていたのだが、そのことにようやくこのとき気付いた。
で、「”小川”は渡れる」ということにも気付いた。
この先に待っている、今から渡ろうとしている「川」はどっちだ…?
「小川」だ。よっしゃ。渡れるじゃん!
この冒険において、大事なことを忘れていた。「進路」を決めるための自分が持っているアイテムは、「マップ」と「コンパス」のみだった。
たいがいアイテムの取扱説明書は読まないことが多いのだが、OMMにおける「マップ」は、穴が開くほどに隅から隅まで見なければいけないものだった。
序盤にそのことに気付いて以降は、”より慎重に”マップに記載されている情報を探すようになった。(これはめちゃくちゃ当然のことなのだが、浮足立って忘れていた。)
事件その③ 意見が食い違う
OMMも「バディ」という面白い制度をよくもまぁこの競技に組み合わせたものだ、と感心する。
もちろん単独より複数のほうが「何かあったときの安全」も確保されるので、そういったセーフティーネット的な役割が最大の目的の制度ではあるのだが、この「チーム」という仕組みが、この競技を何倍も面白く、奥深いものにしているのも間違いない。
「冒険」は、単独よりも複数のほうが、いい意味でも悪い意味でも(?)、より濃密なものになる。
僕ら山猿夫婦の話で恐縮だが、僕ら二人は、端から見たらもしかしたら「仲が良く」見えているかもしれないが、しょっちゅう喧嘩をしている(笑)
ロングトレイルでもOMMでも、長時間一緒に過ごすものはたいてい数回以上は喧嘩をしているのではないだろうか。何回喧嘩しているかは不明だが、ひとつ確実にいえることは、「喧嘩しなかったことはない」ということか(笑)
まぁ人間と人間なんだからそんなもんだろう、と僕は得意の楽観思考で捉えているのだが、もしかしたらそんな”あっけらかん”とした態度がさらに相方の何かに拍車をかけているのかもしれない。
(「”かもしれない”じゃねーよ」という声がどこからか聞こえてくる…)
話が逸れてしまった。失敬失敬。
今回は役割分担を明確化したことで(大まかなルート設計→相方、コントロール近くの慎重な地図読み→僕)、過去のレースに比べればだいぶまともになったと思う。
役割を決めたら、「その担当者が示す意向に基本従う」というルールにした。別にそうしようと話したわけではないが、暗黙の了解でそうなっていった。
これはオリエンテーリング競技ではけっこう大事なポイントで、トップチームも「地図読み担当」「走り担当」「パワフル担当」「盛り上げ担当」などと、役割が分かれていることがほとんど(なはず)。
そんなこんなでいい感じで役割分担をしたものの、それでもやっぱり、何度かは”そんな場面”は訪れた。
「ん?ほんとにそっち?こっちじゃね?」
「いや、絶対行き過ぎだって。」
「これは引き返しといたほうがいい気がするけど。」
などなど。
僕は「あっけらかん野郎」かと思いきや、実はめちゃくちゃ慎重なタイプなので、ちょっとでも不安になると時間をかけて地図を見直したい派。裏返すと、基本自分に自信がない。
一方相方は、一度自分が自信をもって決めた進路については、迷いなく突き進むタイプ。相方のことをご存知の方はなんとなくわかると思うが、OMMにおける「進路決定」に限らず、物事全般において、この「ブレない芯の強さ」が彼女の持ち味だ。
…が、OMMという競技では、これはときに諸刃の剣。
現在地がわからなくなってから、「あれ?ここどこだ?」と地図を見つめ直してもその時は、もう時すでに遅しなのだ。
余程、2Dのマップを「脳内で3D化するスキル」(要は本当の「地図読みスキル」)が備わっていなければ、この時点でもはや「遭難」なのである。
そういう意味では、本当は100mごとに「確実といえる事実」を、回りの景色と地図を見比べながらこれでもかというくらい集めて集めて集めまくって、自信をもってから進むのが、たぶん本来の姿。
ただ、「慎重すぎること」も諸刃の剣であることは言うまでもない。OMMにはコントロール毎に「制限時間」が設定されているからだ。制限時間を設定しなければ、いずれ夜になりさらに「遭難」のリスクが高まるのは間違いないので、これは致し方ない。
つまり何が言いたいかというと、自信をもって突き進む場面(決断)と、慎重に進む場面(決断)、この両者のバランスが必要。
あれ?ここの見出しなんだっけ?あ、そうだ。「意見が食い違う」だ。今回はよう話が逸れる。失敬失敬。
この話を、「意見が食い違う」ということに繋げて強引に着地させたい。
何度も何度も繰り返し申し訳ないが、要は「OMMって超絶楽しい」ってことが、この話の着地になる(笑)
お互いに食い違う意見を、”役割分担”という「仕組み」で対策し、”従順”という「忍耐」でなんとか消化し笑、最終的には相手を「信頼」し、同じゴールを目指して突き進む。
これはもはやヒューマンドラマだ。
ヒューマンドラマ(特にドキュメンタリーもの)が面白いように、OMMはそういう意味でもやっぱり「面白い」。
まぁドラマの当事者になると、面白くないときもあるけれど…笑(でもそこは当事者でしか感じ得ることができない感情・経験として、「人間としての成長」に繋げればいいだけの話だ。)
うん、なんだか綺麗にまとまったので(まとまってない?)、この項はそろそろ終わりにしよう。
もはやOMMのレポートなのか、誰も求めていない僕の哲学を語る場なのか、なんなのかよくわからなくなっているが、次回のレポートもこの調子で続けようと思う。
▼参戦記③はこちら



-300x212.jpg)
-300x212.jpg)
-300x212.jpg)
-300x212.jpg)
-300x212.jpg)
-300x212.jpg)
-9分差の21時間53分08秒(2023年11月18・19日)-300x212.jpg)
-9分差の21時間53分08秒(2023年11月18・19日)-300x212.jpg)
コメント